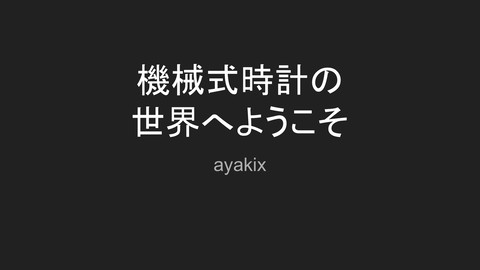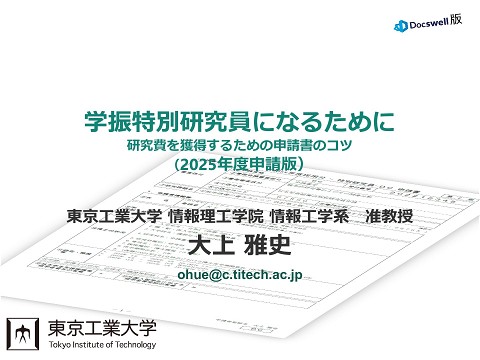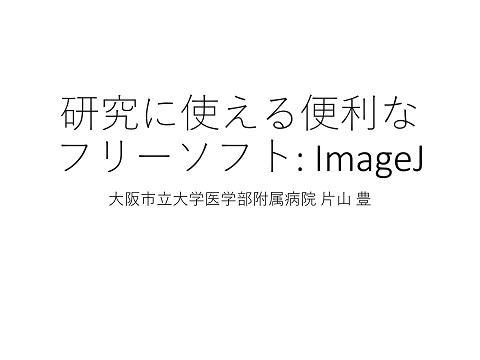時刻と位置特定の秘密を解き明かす〜大航海時代から未来の測位技術へ〜
2.9K Views
September 20, 25
スライド概要
iOSDC 2025 Day 2, Track A, 13:00
本セッションでは、位置情報アプリを開発しているアプリエンジニア、または位置情報技術に興味を持つ方を対象とし、位置情報の「精度」や「時刻の取り扱い」について解説します。
スマートフォンで取得できる位置情報は、地図アプリ、交通サービス、IoT、防災など、日常生活を支える多くのアプリで活用されています。しかし、その位置情報がどのような仕組みで得られているのか、特に時刻情報がどのように関わっているのかについては、普段意識することが少ないかもしれません。
本セッションではまず、古代より人類がどのように時刻を求めてきたかを述べ、位置と時刻を求める人類の挑戦として、18世紀イギリスで制定された「経度法」と、それにより始まった経度問題の解決に向けた競争、そしてジョン・ハリソンによる海洋クロノメーターの開発を振り返ります。次に、電波を使った測位方法の歴史と、GPSをはじめとするGNSS(全地球測位システム)の基本原理を解説し、衛星信号を用いて端末の位置を特定する仕組みを解説します。
さらに、GNSSの生データを取得・解析するための専用ツール「GNSS Logger」と「GNSS Analysis」を活用し、端末が捕捉している衛星の数や種類、方向、信号強度といったデータを可視化します。これにより、都市環境でのマルチパス反射、大気遅延(電離層・対流圏)、衛星の配置や補足数不足といった精度劣化要因が、どのようにデータに現れるのかを具体的に解説します。
最後に、センチメートル級の高精度測位の仕組みと、それがもたらす未来の可能性についての展望を語ります。
聴講後には、位置情報と時刻情報の本質的な関係を理解し、位置特定にまつわる歴史と技術の知識が身につきます。
今日もどっこい生きているアプリエンジニア&バイオリン製作家&ピアニスト&ワイン醸造家。絶望的に道に迷うので、個人で方向音痴向けナビアプリ「Waaaaay!」を作っています。 生八橋、ピーナッツかりんとう、芋けんぴ、ちんすこう、通りもん、抹茶味の食べ物が好き。
関連スライド
各ページのテキスト
時刻と位置特定の秘密を解き明かす 大航海時代から未来の測位技術へ Day 2, Track A, 13:00Ryota AYAKI / @ayakix
位置特定といえば GPS
人類は「より正確な時間」を求めてきた 時代 理由 使用目的 必要な精度 古代 リズムの可視化 暦、農耕、儀式 日単位 中世 秩序の維持 祈り、市場を開く、仕事を始める・終 わる 時単位、共通認識 近世 航海と貿易 位置の確認 分〜秒 単位、基準時 近代 科学と産業 電車のダイヤ、測量 秒単位 現代 ITと測位 衛星測位、インターネット、証券取 引、自動運転 ナノ秒 単位、空間と時間の一体 的な精度 低 高
時計の誕生 –日時計– 紀元前5000年頃のエジプト ナブタ・プラヤ遺跡 影の位置や長さで おおよその季節や時刻を知る 太陽が出ている時しか使えない
時計の誕生 –水時計– 紀元前1400年頃のエジプト 水の流れ出る量で計測 不定時法に対応 蒸発、凍りつくなどの欠点
時計の誕生 –燃焼時計 – 6世紀頃 ローソク、お香、ランプ 燃えた長さで時刻を読み取る 燃やし続ける訳にはいかない
時計の誕生 –砂時計– 14世紀頃 揺れや温度などの環境の変化に強い 海上での時間計測の手段
大航海時代の訪れ 1492年:コロンブスがアメリカ新大陸発見 1498年:ヴァスコ・ダ・ガマがインドへの新航路を発見 1522年:マゼランが世界周航 最大の課題 →船が今どこにいるか?
ログ(log)とノット (knot) ログ=丸太、ノット=結び目 投げ込んでからの時間と距離から 速度を計測 Log book(航海日誌)に記録
緯度の計測 太陽の南中高度 北半球の場合は北極星の高さ 一方で、経度がわからない 六分儀
緯度航法 1. まず南へ下る 2. 目的地と同じ緯度に合わせる 3. そこから東(または西)へ進む 沿岸に進むのはダメ? 南に進んだ後、 南東に進むのはダメ?
磁北と真北 コンパス(羅針盤)の北に進めば北極点に着 く?→NO! 北磁極に着く 日本では、真北に対して磁北が約7度 西側にずれている 正確な方角が分からない そもそも帆船は真っ直ぐ進めない
経度発見への賞金制定 1587年 スペインのフェリペ2世が賞金をかける 1598年 スペインのフェリペ3世が終身年金を出す 1600年ごろ オランダ政府も賞金をかける
経度の計測? 木星の衛星を利用 ガリレオ・ガリレイが1610年に衛星を発見 衛星食の回数は非常に多く、経度測定に利用できる 振り子時計を利用 (日差10分以上) 出発地点の時刻に合わせた時計を持って航海 基準地と観測地の時刻のズレを計測 どちらも 精度不足
ホイヘンスのひげぜんまい 1675年に制作「世界初の実用的な機械式時計」 日差が1分ほどに
航海で求める日差の条件 赤道付近の経度1度の差は約111km。最大でも1度以内の誤差 24 時間 (1440 分) ÷ 360 度 = 4 分 ▶4 分時計が狂うと経度が1度狂う 4 分 (240 秒) ÷ 40 日 = 日差 6 秒以内
経度法の制定 1707年:英国の軍艦4隻が座礁、約2,000名の死亡者を出す 1714年:イギリス議会が経度法を成立 経度1度以内の誤差 ▶1万ポンド 3分の2度以内の誤差▶1.5万ポンド 2分の1度以内の誤差▶2万ポンド(現在の数億円規模) 経度審査委員会の発足 物理学担当:ニュートン / 天文学担当:ハレー
ジョン・ハリソンの登場 1693-1776、本職は大工 1730-1735年にH1を開発 木製の歯車 1736年リスボンに向かう航海 1737年:経度委員会が初招集 満足せず、改良を申し出る 賞金の一部 500ポンドを授与 H 63 cm, W 68 cm, D45 cm, 34 kg
H2(H1から2年後) 1737-1739年にH2を開発 小型化、気温変化に対応 オーストリア継承戦争勃発 & 実験の延期 満足せず、改良を申し出る 賞金の一部 500ポンドを授与 H 68 cm, 39 kg
H3(H2から1年後) 1740-1757年(17年!!)にH3を開発 振り子式からの脱却 イギリスは七年戦争 洋上実験できず ハリソンこの時 64歳 H 62 cm, W 30cm, 27 kg
H4(H3から2年後) 1755-1759年にH4を開発 1761年にカリブ海ジャマイカまでの 洋上実験 81日間で誤差は5.1秒 目標クリア!! 165mm x 124 mm x 28mm 1.45 kg
天体観測派の妨害工作 貴族や学者で構成される天体観測派 vs. 階級の低い職人 別の職人が同じもの作れないとダメなようにルール変更 - ラーカム・ケンドールがK1を作り、同じような精度 - 試験にはキャプテン・クックの世界周航 ドイツのマイヤーが月距法で経度を計測できるように計算表を作成 - 未亡人に賞金を与えてメンツを立てる 1773年:国王ジョージ3世への直訴、賞金の全額授与 (この時80歳, 3年後死去)
電波航法の誕生
ロラン( LORAN: Long Range Navigation) 1940年代初頭 信号の到達時間差を利用 今居る場所=双曲線の交点 精度は数百m 電波の到達範囲は 1,000kmほど 図参考 https://www.rf-world.jp/bn/RFW07/samples/p039-040.pdf
オメガ航法 1968年〜 電波の到達距離1万km超 8つの基地局で地球全域をカバー 1,000m〜2,000mの精度 大きなアンテナと受信設備 高さ454mの対馬オメガ局
Transit衛星 1957年ロシアのスプートニク1号の打ち上げを受けて 1960年代に米海軍が開発 ドップラー効果を利用 原子力潜水艦の位置測定 長時間受信する必要
航空機やミサイルの位置測定 米空軍のニーズ 移動する自機の位置を継続的&素早く測定 高度を加えた3次元の位置測定 GPSのルーツとなる 「プロジェクト 621B」
GPSの誕生 1. 2. - セシウム原子時計を搭載:数ナノ秒(10億分の1秒)単位 1ナノ秒のズレ = 30cmの位置誤差 全世界をカバーするためには24機必要 冷戦による巨額の出資(20年間で1兆2000億円) 位置計算のために4機の衛星から電波を同時に受信 90年に民間開放、2000年まで誤差100m→後に数m~十数m
各国のGNSS (Global Navigation Satellite System) GPS: アメリカ QZSS(みちびき): 日本 GLONASS: ロシア NavIC: インド Galileo: 欧州 BeiDou (北斗): 中国 130機以上による測位 マルチGNSSによる精度向上
GNSS Logger GNSS Analysis https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/sensors/gnss
損 ←データの欠 駅での停車中 → ゆりかもめ乗車中の RAWデータ
位置の補正処理 - 緑:RAWデータ - 青:カルマンフィルタ - 赤:ADR (累積デルタ距離)
標高=楕円体高 – ジオイド高 楕円体高:地球の平均的な形からの高さ ジオイド高:海面の平均的な高さ 標高 楕円体高 ジオイド高 楕円体 海面
ジオイド 図参考 https://qzss.go.jp/overview/column/geoid_151225.html
センチメートル級の測位の必要性 - 建設(ICT施工) 農業(スマート農業・自動トラクター) ドローン測量 自動運転(高精度マップ作成 / 自己位置推定) GNSSの限界 - 衛星の軌道の誤差 - 電波が大気を通る際の遅延 - ビルや地形による反射
RTK (Real Time Kinematic) GNSS 移動局 補正情報を送信 電波が大気を通る際の遅延 衛星の軌道の誤差 基準局
センチメートル級の測位 - ネットワーク型RTK DGPS (Differential GPS:差分GPS) PPK(Post-Processed Kinematic) PPP(Precise Point Positioning:精密単独測位)
まとめ - 時計の歴史と精度への挑戦 - 時間と空間の精度の結びつき - 社会インフラとしての時間と場所の測位 - ナノ秒単位 - cm単位 時間と空間の「精度」が支える未来社会
余談
UTCとGMT 1秒は「セシウム133原子が91億9263万1770回振動する時間」 セシウム原子の振動数をもとに導き出すUTCの方が正確な時間のため今はUTCが使 われています。