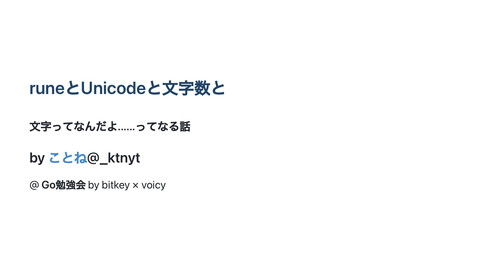AI境界値分析で 回帰テスト作成を自動化してみる
818 Views
July 23, 25
スライド概要
久々のやってみた系発表でした
関連スライド
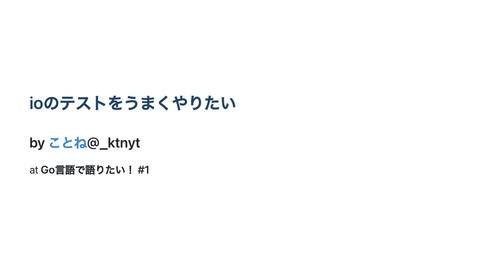
ioのテストをうまくやりたい

Meta XR SDK(V66-74)でQuestアプリを開発
各ページのテキスト
AI境界値分析で 回帰テスト作成を自動化してみる AI生成コードのレビューがつらい…“品質”をどう守る?現場の知見共有会 Mirei Itaya (Kotone) - 2025/07/23
自己紹介 ことね(板谷美玲) • LAPRAS株式会社 • ソフトウェア開発者です • アジャイル開発が好きです • 人を生き生きとさせるのが好きです • FF14にハマってます • 鳥と暮らしてます
なぜ「回帰テスト」なのか
「品質が高い」とは? ソフトウェアにおける品質の高低をどう判断するのか 結論:ユーザー体験 (UX) の高さ コードの「きれいさ」は開発者体験に影響する 開発者体験は開発生産性に影響する 開発生産性はエンドユーザーにとってはどうでもいい ただし開発生産性が結果的に上がることはある
「ユーザー体験」とは? エンドユーザーは何を以てして「良い体験」をするのか テクノロジーを意識することなく目的を達成できること 初代MacのGUI→WYSIWYG iPhoneのタッチパネル→直感的操作 LLMエージェント→自然言語インタラクション
ユーザー体験を高めるには? テクノロジーとの摩擦を減らす方法 人間の特性を活かした実装が重要 動作を減らす→同じことを少ない操作で実現する コンテキスト削減→大きな描画を減らす フィードバック→何が起きているかを明確にする 習慣を活用する→奇を衒わない、破壊的変更をしない
デグレ(回帰)をテストで防ぐ 回帰の有無を確認するから「回帰テスト」 前提として意図的な破壊的変更は避けるべき 例:ボタンの配置を変える→操作方法を再学習しなければならない 例:設定ファイルの参照先を変更する→突然環境が壊れる 意図しない破壊的変更はもっと避けるべき(起こしてはならない) インシデントはだいたい意図しない破壊的変更に起因する
AIは平気で既存動作を壊す 小規模ペーパークリップ問題 良くも悪くもLLMは指示されたこと「だけ」を達成しようとする 1. 指示が間違っている→人間の問題 2. 指示の意図を誤解する→コンテキストが不足している 3. 楽をしようとする→「テストが失敗しているのでテストを消そう!」
AIは余事象の機能的推論が苦手 AIが生成したコードをレビューすることがなぜつらいのか? 「数字が偶数であることを判定する関数を実装して」 Web系の言語の多くは動的型付け (Python/Ruby/JavaScript…) 浮動小数が渡されたら?文字列が渡されたら? テスト駆動開発をすれば動作を保証できる 型を使うと特定の事前条件を棄却できる
AIの破壊衝動と付き合っていくには? 人間を介さずにいかにAIの行動を制限できるか Claude Codeは複数の方法が実装されている Tools→外部リソースからのコンテキスト注入を自動化 Commands→定型文の入力を自動化 Hooks→フォーマッタ、リンタ、テストの実行を自動化 機械的に制約できることを増やすと人間の介入が減る
機械的制約がAIの真価を引き出す
AI自身に制約を作らせられる? 回帰テストの実装をどこまで自動化できるのか 1. プログラムのロジックを読解させる 2. ロジックの境界値分析を実施させる 3. テストすべき境界値をチェックリスト形式で保存する 4. チェックリストに対してテストを実装させる 5. 境界値の網羅率を機械的にチェックする←これは自動化できそう
Coverage Checker Pythonの境界値網羅率チェックツール 1. 関数のdocstringを確認する 2. チェックリストがない場合は「未カバー」としてマーク 3. 境界値に対応するテストが存在するか確認 4. 存在するか否かに応じて自動的にチェックをつけ外しする 5. 結果を報告する
デモタイム
しばらく運用してみた所感 良かったこととか悪かったこととか ✅ 境界値の条件とテストの実装を読めば中身をある程度信用できる ✅ 全自動でテストを書いてくれるので人間の工数はゼロで楽 ❌ それなりに時間がかかる ❌ 無視してよい事前条件もテストしてしまう 境界値は人間が設定したほうがいいのかもしれない
Tips & Tricks 良いコード・テストを出力させる工夫 イント 振る舞いの局所性 (Locality of Behavior) を上げる コードの検索性 (Code Discoverability) を上げる ドキュメントをちゃんと書く(書かせる) E2E/Pinningテストだけを残して定期的に全部捨てる ポ 結局AIに作らせる最大のメリットは気軽に消せること
cclsp: LLM用LSP MCP npx cclsp@latest setup 参照先の発見 定義元の発見 一括リネーム Diagnostics取得
結局まだ仕組みが足りない Claude Codeがんばって LSP機能はIDE頼りじゃなくて組み込むべき IDEが繋がっていてもFind/Grepを多用するのはなんとかしてほしい Todoリストと併用できるチェックリストを運用したい チューリング完全なHooksの仕組みがあったほうがいい 逆に言えばコーディングエージェントは伸びしろがありそう